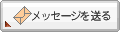2010年05月19日
大和世(やまとゆー)60
今帰仁村 運天港 海軍基地 13 / 最終章
今帰仁村 上運天と名護市屋我地島 運天原の間に広がる、天然の良港。
敢無く潰えた運天港 海軍基地の最後。
昭和20年3月30日未明、海軍沖縄方面根拠地隊司令は、麾下部隊に訓電を発す。 電文には「・・・皇国防衛ノ大任ヲ有スル吾等 正ニ秋水ヲ払ヒテ決然起ツベキノ秋ナリ・・・」と記されるも、運天基地に払うべき剣は、手負いの甲標的丙型2杯のみ。 蟷螂の斧であろう事は、火を見るよりも明らかな事であった。
訓示した司令自身、兵員、装備の不足は承知しており、斯様な状況下で戦闘状態に突入した将の心情を思へば、訓電は悲痛にさへ聞こえる。
3月30日晩、甲標的1杯が出撃するも、故障により会敵出来ず、翌31日に帰投。
4月1日、米軍は嘉手納海岸に上陸を開始。 絶え間無い空爆に、充電、魚雷の装填等、整備、出撃準備も難航。 併せて古宇利島、備瀬埼にも小型艦艇が遊弋し、出撃もままならなかった。
4月5日、甲標的2杯は最後の出撃をする。 予てより厳重な警戒を為す敵艦船に、接近の機会は得られず、遠距離からの魚雷攻撃のみで反転、帰投した。
運天港は連日の空襲に桟橋、道路の港湾施設が破壊され、基地機能は失われていた。 北上する敵地上軍は、名護に接近しつつあり、第27魚雷艇隊は陸戦部隊に移行、第2蛟龍隊にも陸戦移行の命令が下る。
出撃した2杯が帰投すると、基地施設を破壊、殊勲の甲標的2杯も自沈。 此処に於いて、運天海軍基地は完全に機能を停止、潰え去った。
陸戦に移行した両隊は、八重岳、乙羽岳、久志岳と転戦。 激戦に疲弊した第2蛟龍隊は6月7日に部隊を解散、隊長は南部戦線への突破を決するが、敵わぬ事であった。 第27魚雷艇隊は、終戦後の9月3日、米軍に投降したと云う。
乏しい装備で、敢然と敵の刃に立ち向った両隊。 しかしながら、陸戦移行後、附近住民への徴発、恫喝行為は、汚名として語られている。 特に第27魚雷艇隊の行った、愛楽園での食料徴発は、正史に残る。
運天を発ち、還る事の無かった搭乗員。 夜を徹しての出撃準備をした基地員。 八重岳に斃れた将兵。 彼等の心情を思へば、如何に生死を分かつ極限状態とは云へ、残念な限りである。
斯様な事にも拠るのか、此処運天に今、かつての海軍部隊を記す標は、何処にも見られない。
運天港口(2004年9月撮)
上運天の展望台から臨む、運天港の港口。
碧い海に白く伸びる古宇利大橋は、画の様にさへ見へる。

かつての桟橋位置
基地員が、徹夜で出撃準備をした、旧桟橋位置。
此処を発って戻る事の無かった蛟龍2杯。 今でも西海岸の海底の何処か、乗員を擁いたままに眠っている。 運天基地、沖縄戦の末期も知らぬままに。

出撃の際の水路、古宇利水道
今帰仁村総合運動公園から望む、古宇利水道。
フレーム左端の白く波立つ箇所にリーフが広がる。 潜航艇の様に喫水の深い船は、古宇利島寄りにしか可航水域が得られない。
戻らなかった艇搭乗員には、此処が野辺の路となった。 あまりにも碧い、そして澄み切った野辺の路。

今帰仁村 上運天と名護市屋我地島 運天原の間に広がる、天然の良港。
敢無く潰えた運天港 海軍基地の最後。
昭和20年3月30日未明、海軍沖縄方面根拠地隊司令は、麾下部隊に訓電を発す。 電文には「・・・皇国防衛ノ大任ヲ有スル吾等 正ニ秋水ヲ払ヒテ決然起ツベキノ秋ナリ・・・」と記されるも、運天基地に払うべき剣は、手負いの甲標的丙型2杯のみ。 蟷螂の斧であろう事は、火を見るよりも明らかな事であった。
訓示した司令自身、兵員、装備の不足は承知しており、斯様な状況下で戦闘状態に突入した将の心情を思へば、訓電は悲痛にさへ聞こえる。
3月30日晩、甲標的1杯が出撃するも、故障により会敵出来ず、翌31日に帰投。
4月1日、米軍は嘉手納海岸に上陸を開始。 絶え間無い空爆に、充電、魚雷の装填等、整備、出撃準備も難航。 併せて古宇利島、備瀬埼にも小型艦艇が遊弋し、出撃もままならなかった。
4月5日、甲標的2杯は最後の出撃をする。 予てより厳重な警戒を為す敵艦船に、接近の機会は得られず、遠距離からの魚雷攻撃のみで反転、帰投した。
運天港は連日の空襲に桟橋、道路の港湾施設が破壊され、基地機能は失われていた。 北上する敵地上軍は、名護に接近しつつあり、第27魚雷艇隊は陸戦部隊に移行、第2蛟龍隊にも陸戦移行の命令が下る。
出撃した2杯が帰投すると、基地施設を破壊、殊勲の甲標的2杯も自沈。 此処に於いて、運天海軍基地は完全に機能を停止、潰え去った。
陸戦に移行した両隊は、八重岳、乙羽岳、久志岳と転戦。 激戦に疲弊した第2蛟龍隊は6月7日に部隊を解散、隊長は南部戦線への突破を決するが、敵わぬ事であった。 第27魚雷艇隊は、終戦後の9月3日、米軍に投降したと云う。
乏しい装備で、敢然と敵の刃に立ち向った両隊。 しかしながら、陸戦移行後、附近住民への徴発、恫喝行為は、汚名として語られている。 特に第27魚雷艇隊の行った、愛楽園での食料徴発は、正史に残る。
運天を発ち、還る事の無かった搭乗員。 夜を徹しての出撃準備をした基地員。 八重岳に斃れた将兵。 彼等の心情を思へば、如何に生死を分かつ極限状態とは云へ、残念な限りである。
斯様な事にも拠るのか、此処運天に今、かつての海軍部隊を記す標は、何処にも見られない。
運天港口(2004年9月撮)
上運天の展望台から臨む、運天港の港口。
碧い海に白く伸びる古宇利大橋は、画の様にさへ見へる。

かつての桟橋位置
基地員が、徹夜で出撃準備をした、旧桟橋位置。
此処を発って戻る事の無かった蛟龍2杯。 今でも西海岸の海底の何処か、乗員を擁いたままに眠っている。 運天基地、沖縄戦の末期も知らぬままに。

出撃の際の水路、古宇利水道
今帰仁村総合運動公園から望む、古宇利水道。
フレーム左端の白く波立つ箇所にリーフが広がる。 潜航艇の様に喫水の深い船は、古宇利島寄りにしか可航水域が得られない。
戻らなかった艇搭乗員には、此処が野辺の路となった。 あまりにも碧い、そして澄み切った野辺の路。

Posted by 酉 at 12:00│Comments(0)
│景 色