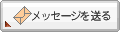2014年11月17日
沖縄に潰えた軍旗 11
歩兵第22聯隊 11
通称号 山3474部隊、第24師団 歩兵第22聯隊の軌跡
(都屋海岸の聯隊砲陣地 2)
昭和19年7月6日、歩兵第22聯隊に動員が下令、第24師団はソ満国境警備の任を解かれ、南方派遣軍へ編入される。 これは同じ月、サイパン島守備隊の全滅、グァム、テニアンへも敵は上陸、掛かる沖縄の戦略的価値から、大本営の行った沖縄諸島の防衛を担当する第32軍の兵力増強であった。 この月、第9師団が沖縄へ上陸、更に第24師団、第62師団が続き、この時は3コ師団・1コ独立混成旅団により沖縄本島を守る計画であった。
この時、聯隊は戒名ともなる「山3474」の通称号を授けられる。 部隊は島嶼守備に編成替えが行われ、行李隊、弾薬小隊は除かれ、馬匹も最小限の5頭に限られた。 出発は7月12日~14日の何れも深夜、第3大隊、第2大隊と歩兵砲大隊、そして聯隊本部と通信中隊に分かれ、西東安を発った軍用列車は釜山へと向かった。
釜山に集結した師団は16~17日に掛け、連絡船によって博多へと移動、再び鉄路を熊本へ移動し、12日間を駐屯する。 ソ満国境から初夏の九州への移動は堪えたらしく、この間に長旅の疲れを癒し、併せて学校のプールでは乗船の遭難を想定して避難訓練が行われた。
昭和19年8月1日、熊本を出発し門司港に到着、この度は集結した船団に師団全てが乗船し出港した。 目的地は告げられていなかったが、出港後、将校には2枚の地図が渡される。 地図の1枚は5万分の1 沖縄島全図、他の1枚は2万5千分の1 沖縄中部地形図、その読み慣れない地名を沖縄出身の軍医から、部隊長以下の将校は説明を受けた。
船団は台風の荒波を衝いてシナ海を南下、同年8月5日の朝、無事に金武湾へ到着する。
都屋の岩場
今や沖は防波堤に囲まれ、汀はスリップのコンクリートに埋められている。
通称をアミフシモー(網干し毛)と呼ばれた岩場から迫り出した岬、この下の海蝕洞を利用し砲座は設けられた。

洞穴の一部
奥まった位置に半ば埋め潰された洞穴が開き、やや距離を置いて銃眼が残存する。

通称号 山3474部隊、第24師団 歩兵第22聯隊の軌跡
(都屋海岸の聯隊砲陣地 2)
昭和19年7月6日、歩兵第22聯隊に動員が下令、第24師団はソ満国境警備の任を解かれ、南方派遣軍へ編入される。 これは同じ月、サイパン島守備隊の全滅、グァム、テニアンへも敵は上陸、掛かる沖縄の戦略的価値から、大本営の行った沖縄諸島の防衛を担当する第32軍の兵力増強であった。 この月、第9師団が沖縄へ上陸、更に第24師団、第62師団が続き、この時は3コ師団・1コ独立混成旅団により沖縄本島を守る計画であった。
この時、聯隊は戒名ともなる「山3474」の通称号を授けられる。 部隊は島嶼守備に編成替えが行われ、行李隊、弾薬小隊は除かれ、馬匹も最小限の5頭に限られた。 出発は7月12日~14日の何れも深夜、第3大隊、第2大隊と歩兵砲大隊、そして聯隊本部と通信中隊に分かれ、西東安を発った軍用列車は釜山へと向かった。
釜山に集結した師団は16~17日に掛け、連絡船によって博多へと移動、再び鉄路を熊本へ移動し、12日間を駐屯する。 ソ満国境から初夏の九州への移動は堪えたらしく、この間に長旅の疲れを癒し、併せて学校のプールでは乗船の遭難を想定して避難訓練が行われた。
昭和19年8月1日、熊本を出発し門司港に到着、この度は集結した船団に師団全てが乗船し出港した。 目的地は告げられていなかったが、出港後、将校には2枚の地図が渡される。 地図の1枚は5万分の1 沖縄島全図、他の1枚は2万5千分の1 沖縄中部地形図、その読み慣れない地名を沖縄出身の軍医から、部隊長以下の将校は説明を受けた。
船団は台風の荒波を衝いてシナ海を南下、同年8月5日の朝、無事に金武湾へ到着する。
都屋の岩場
今や沖は防波堤に囲まれ、汀はスリップのコンクリートに埋められている。
通称をアミフシモー(網干し毛)と呼ばれた岩場から迫り出した岬、この下の海蝕洞を利用し砲座は設けられた。

洞穴の一部
奥まった位置に半ば埋め潰された洞穴が開き、やや距離を置いて銃眼が残存する。

Posted by 酉 at 12:00│Comments(0)
│戦争遺跡