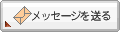2010年01月04日
戦世(いくさゆー) 11
与那原町 (馬天)射堡指揮所 1
与那原町 板良敷の斜面に残る、射堡の指揮所跡。
佐世保海軍施設部の指揮下、住民の勤労動員とによって建設された。
先ず、「射堡(しゃほ)」とは何か。
陸上から沖合いの艦船を目掛けて、魚雷を発射する施設を云い、戦前は関門港にも防備/閉塞の為に存在した。 本来は、旋回式の魚雷発射管を波打ち際の岸壁や壕に据え付け、測的諸元に見合った方位角(発射角)に定め、魚雷を圧縮空気で発射する。 下関にその名残りを留める設備は、関門港の東西、約180度の方位を見渡す発射管と、背後には次発装填用の魚雷格納庫(隧道)を構築していた。
此処では同地の斜面に、指揮所と並列構築された「魚雷調整壕」(格納壕)の横穴から、海岸端までをレールで結び、指揮所の発射命令に従って、台車に据え付けた魚雷を走らせる、いわゆる発射をした。 台車は斜面を駆け下りて加速、途中で主機関を起動し、干瀬を渡って海中に入り、台車から離れて海中を標的へと推進して行く…計画であった。
昭和19年後半、佐世保鎮守府の沖縄(南西諸島)防備計画の一環として、海岸砲「海軍砲台」の設営が、本島各処で為された。 「射堡」もそれと同時期、不足する機雷堰/海岸砲/沿岸砲の穴を埋める為、島内20箇所へ設置する計画を立案していた。
魚雷自体は、搭載する艦艇/航空機も不足した時分でもあり、旧式の物も調整、射堡基地用に融通し、配備が行われた。
しかし、魚雷調整班の編成と場所の選定もが滞り、昭和19年中に完成した設備は2箇所に留まる。 そしてそのまま米軍の上陸を迎える事となった。 馬天以外の1箇所は旧佐敷町内と思慮されるが、詳細は不明。 慶良間への配備は、全くの見当違いによって見送られたと云う。
地所は与那原町 板良敷になるものの、文献通称の「馬天射堡」基地として記しています。
馬天射堡指揮所の外観
左面に見えるのは展視口、此処から方位/距離の測的を行った。

与那原町 板良敷の斜面に残る、射堡の指揮所跡。
佐世保海軍施設部の指揮下、住民の勤労動員とによって建設された。
先ず、「射堡(しゃほ)」とは何か。
陸上から沖合いの艦船を目掛けて、魚雷を発射する施設を云い、戦前は関門港にも防備/閉塞の為に存在した。 本来は、旋回式の魚雷発射管を波打ち際の岸壁や壕に据え付け、測的諸元に見合った方位角(発射角)に定め、魚雷を圧縮空気で発射する。 下関にその名残りを留める設備は、関門港の東西、約180度の方位を見渡す発射管と、背後には次発装填用の魚雷格納庫(隧道)を構築していた。
此処では同地の斜面に、指揮所と並列構築された「魚雷調整壕」(格納壕)の横穴から、海岸端までをレールで結び、指揮所の発射命令に従って、台車に据え付けた魚雷を走らせる、いわゆる発射をした。 台車は斜面を駆け下りて加速、途中で主機関を起動し、干瀬を渡って海中に入り、台車から離れて海中を標的へと推進して行く…計画であった。
昭和19年後半、佐世保鎮守府の沖縄(南西諸島)防備計画の一環として、海岸砲「海軍砲台」の設営が、本島各処で為された。 「射堡」もそれと同時期、不足する機雷堰/海岸砲/沿岸砲の穴を埋める為、島内20箇所へ設置する計画を立案していた。
魚雷自体は、搭載する艦艇/航空機も不足した時分でもあり、旧式の物も調整、射堡基地用に融通し、配備が行われた。
しかし、魚雷調整班の編成と場所の選定もが滞り、昭和19年中に完成した設備は2箇所に留まる。 そしてそのまま米軍の上陸を迎える事となった。 馬天以外の1箇所は旧佐敷町内と思慮されるが、詳細は不明。 慶良間への配備は、全くの見当違いによって見送られたと云う。
地所は与那原町 板良敷になるものの、文献通称の「馬天射堡」基地として記しています。
馬天射堡指揮所の外観
左面に見えるのは展視口、此処から方位/距離の測的を行った。

Posted by 酉 at 12:00│Comments(0)
│戦争遺跡