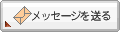2019年08月11日
沖縄県外の戦争遺跡 115
北海道根室市 海軍 根室特設見張所 前篇
根室半島の南岸、太平洋に臨む岬角
夏草に埋もれる望楼の基礎と建屋の土塁
近年、筆者は渡沖の回数を減らしている。 何しろ夏時季の沖縄は草木の繁茂、危険生物の跳梁著しく、加えて暑気はオッサンの身体に応え、短い冬に主な活動を移した。 従前は渡沖していた初夏、秋口だが、変わって根釧台地へ足を向けている。
数年前、歩兵第89聯隊(山3476)の編制、第24師団の衛戍地として、旭川の第7師団(ダイシチシダン)跡を訪ね、帰路に苫小牧の海岸防御陣地を散策したのが発端。 帰宅後に道内の歴史を辿った処、日米開戦後、陸海軍は米国領に近い根室半島への敵襲を恐れ、泥縄の陣地構築に着手。 敗戦により徒労に終わった防御施設だが、系統的な調査成果物はなく、断片的な情報に基づき実踏、記録するようになった次第である。
昭和18年9月、絶対国防圏の決定と前後し、根室半島では海軍が牧の内航空基地の設営に着手。 陸軍は警備隊を編制し、半島の要塞化が図られていった。
牧の内航空基地では軍用線(国鉄牧之内線)が敷設され資材の搬入に用いられた。 しかし土木機械は乏しく厳冬期に工事は停滞し、滑走路の完成に2年の歳月を要する。 駐屯の警備隊は、歩兵2コ大隊程度の兵力で延長100キロの海岸防御を負わされ、散兵壕、特火点の構築に着手。 後に汀作戦から内陸持久へ作戦方針の転換、第7師団からの主力到着後の予備陣地構築など、警備司令以下の将兵は振り回される。
海軍 根室特設見張所の構築は、警備隊長の手記では昭和19年7月頃である。 海軍は既に牧の内で基地設営を進め、配備する機体の開発製造、搭乗員の養成は芳しくなくとも、基盤施設の整備は推進していた。
東西に海岸線が延びる根室半島の南岸で、突出したヒキウス岬は眺望に優れ、対空対水上監視の適地として、監視任務を負った厚岸防備隊の下、新たに設置されたと考えられる。
海軍 根室特設見張所跡
歯舞1丁目、ヒキウス岬の地先に放置された根室特設見張所の跡。
最も顕著な構造物、土塁に囲われたコンクリート製の土台は、監視哨の基礎であったと云われる。

根室半島の南岸、太平洋に臨む岬角
夏草に埋もれる望楼の基礎と建屋の土塁
近年、筆者は渡沖の回数を減らしている。 何しろ夏時季の沖縄は草木の繁茂、危険生物の跳梁著しく、加えて暑気はオッサンの身体に応え、短い冬に主な活動を移した。 従前は渡沖していた初夏、秋口だが、変わって根釧台地へ足を向けている。
数年前、歩兵第89聯隊(山3476)の編制、第24師団の衛戍地として、旭川の第7師団(ダイシチシダン)跡を訪ね、帰路に苫小牧の海岸防御陣地を散策したのが発端。 帰宅後に道内の歴史を辿った処、日米開戦後、陸海軍は米国領に近い根室半島への敵襲を恐れ、泥縄の陣地構築に着手。 敗戦により徒労に終わった防御施設だが、系統的な調査成果物はなく、断片的な情報に基づき実踏、記録するようになった次第である。
昭和18年9月、絶対国防圏の決定と前後し、根室半島では海軍が牧の内航空基地の設営に着手。 陸軍は警備隊を編制し、半島の要塞化が図られていった。
牧の内航空基地では軍用線(国鉄牧之内線)が敷設され資材の搬入に用いられた。 しかし土木機械は乏しく厳冬期に工事は停滞し、滑走路の完成に2年の歳月を要する。 駐屯の警備隊は、歩兵2コ大隊程度の兵力で延長100キロの海岸防御を負わされ、散兵壕、特火点の構築に着手。 後に汀作戦から内陸持久へ作戦方針の転換、第7師団からの主力到着後の予備陣地構築など、警備司令以下の将兵は振り回される。
海軍 根室特設見張所の構築は、警備隊長の手記では昭和19年7月頃である。 海軍は既に牧の内で基地設営を進め、配備する機体の開発製造、搭乗員の養成は芳しくなくとも、基盤施設の整備は推進していた。
東西に海岸線が延びる根室半島の南岸で、突出したヒキウス岬は眺望に優れ、対空対水上監視の適地として、監視任務を負った厚岸防備隊の下、新たに設置されたと考えられる。
海軍 根室特設見張所跡
歯舞1丁目、ヒキウス岬の地先に放置された根室特設見張所の跡。
最も顕著な構造物、土塁に囲われたコンクリート製の土台は、監視哨の基礎であったと云われる。

Posted by 酉 at 12:00│Comments(0)
│県外の戦争遺跡