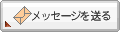2010年09月23日
開発の影で消える戦跡 62
那覇市 おもろまち西方 6
那覇市北部に位置する高台、新都心として開発が為された地域。
新都心の一隅、上之屋に残された高眞佐理の杜。
ここで雨宿りに立ち寄った、通称「高眞佐理」/「高真佐利」(たかまさい)について。
那覇市教委の設置した、古びた説明版に拠れば、正式名称を「与那覇勢頭豊見親 逗留旧跡碑(ヨナハセドトゥイミャー トウリュウキュウセキヒ)」と称する、那覇市指定の史跡/文化財が祭られた拝所。
与那覇勢頭豊見親(よなはせどとぅいみやー)は宮古島の人で、宮古の人では初めて1390年に中山王に服属し、宮古の首長に任じられた。 当初は方言(島言葉)の違いから言葉が通じなかった。 しかし、部下20名に言葉を学ばせ、3年後には直接の朝貢も許され、宮古島へ帰る際は、宮中での送別の宴も催されたと云う。
豊見親(とぅいみやー)の部下の一人「高眞佐理屋」(屋号:たかまさいや)は、毎夜此処、泊後方の高台に登り、アヤグ(宮古の民謡)を謡い、遠く離れた宮古島の故郷を想っていた。 その為、村の人々は此処を「高眞佐理屋原」(たかまさいやばる)と呼ぶ様になったと云う。
(とぅいみやー / とぅいみゃー = 頼み親:宮古で云う親方 /権力者)
杜の場所は、豊見親の屋敷跡で井戸跡(豊見親井:とぅーみゃがー)もあり、人手に渡ったこの土地を後に子孫が買い取り、拝礼の為、1767年に碑を建立したとの事。
激戦地ゆえ碑は戦禍に遇い、上半分を破壊されたものの、教委は昭和62年に復元。 しかしながら不遇は続き、この頃(2004年)と思うが、香炉を破壊された、持ち去られたとの報道を紙上に見た記憶がある。 また、ここで酒盛りをする不届き者も居る様で、雑然とした聖地との記憶は今も拭えない。
現在、泊配水池の据わる高台も、かつては松の木が自生。 高眞佐理の松林と云われ、差し詰め垣花/蚊坂の体であったと思われる。 (泊小学校のHPご参照) しかし、戦火と松喰い虫、そして止め処なき開発に潰え、高台には今、松の木は一筋も立っていない。
木立の中の旧跡碑
与那覇勢頭豊見親の住居跡に建立され、拝所となっている。 松は無く、ガジュマルの緑の中ではあるが、周辺では数少ない緑地。 しかし、雑然とした記憶を裏付ける様に、これ以外の写真は撮影していない。

那覇市北部に位置する高台、新都心として開発が為された地域。
新都心の一隅、上之屋に残された高眞佐理の杜。
ここで雨宿りに立ち寄った、通称「高眞佐理」/「高真佐利」(たかまさい)について。
那覇市教委の設置した、古びた説明版に拠れば、正式名称を「与那覇勢頭豊見親 逗留旧跡碑(ヨナハセドトゥイミャー トウリュウキュウセキヒ)」と称する、那覇市指定の史跡/文化財が祭られた拝所。
与那覇勢頭豊見親(よなはせどとぅいみやー)は宮古島の人で、宮古の人では初めて1390年に中山王に服属し、宮古の首長に任じられた。 当初は方言(島言葉)の違いから言葉が通じなかった。 しかし、部下20名に言葉を学ばせ、3年後には直接の朝貢も許され、宮古島へ帰る際は、宮中での送別の宴も催されたと云う。
豊見親(とぅいみやー)の部下の一人「高眞佐理屋」(屋号:たかまさいや)は、毎夜此処、泊後方の高台に登り、アヤグ(宮古の民謡)を謡い、遠く離れた宮古島の故郷を想っていた。 その為、村の人々は此処を「高眞佐理屋原」(たかまさいやばる)と呼ぶ様になったと云う。
(とぅいみやー / とぅいみゃー = 頼み親:宮古で云う親方 /権力者)
杜の場所は、豊見親の屋敷跡で井戸跡(豊見親井:とぅーみゃがー)もあり、人手に渡ったこの土地を後に子孫が買い取り、拝礼の為、1767年に碑を建立したとの事。
激戦地ゆえ碑は戦禍に遇い、上半分を破壊されたものの、教委は昭和62年に復元。 しかしながら不遇は続き、この頃(2004年)と思うが、香炉を破壊された、持ち去られたとの報道を紙上に見た記憶がある。 また、ここで酒盛りをする不届き者も居る様で、雑然とした聖地との記憶は今も拭えない。
現在、泊配水池の据わる高台も、かつては松の木が自生。 高眞佐理の松林と云われ、差し詰め垣花/蚊坂の体であったと思われる。 (泊小学校のHPご参照) しかし、戦火と松喰い虫、そして止め処なき開発に潰え、高台には今、松の木は一筋も立っていない。
木立の中の旧跡碑
与那覇勢頭豊見親の住居跡に建立され、拝所となっている。 松は無く、ガジュマルの緑の中ではあるが、周辺では数少ない緑地。 しかし、雑然とした記憶を裏付ける様に、これ以外の写真は撮影していない。

Posted by 酉 at 12:00│Comments(0)
│旧跡・文化