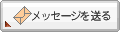2012年10月17日
大和世(やまとゆー) 203
糸満市糸満 白銀堂 / 前篇
古より糸満の人々が絶えず訪れる聖地。
今も糸満の生活、祭祀の中心にあって崇め奉られている。
糸満ロータリーの北方、徒歩数分の位置に鎮座する御社。 那覇からの国道331号線に面し、歩道脇の鳥居は顕著に佇み、その名を冠するバス停も存する。 信仰の対象として南部では著名な場所ながら、神主の常駐する神社ではなく、小ぢんまりとした拝所。 当然ながら、観光客の訪れる処ではない。
その白銀堂、方言では「イービンメー」と呼ばれるらしいが、その正確な創建年代は不明。 1713年成立の『琉球国由来記』、その文章の中には「シロカネ」の記載が見られ、それは18世紀の以前と思われる。 その後明治25年、第4代沖縄県知事に就任した奈良原繁 、彼によって「白銀堂」の名が命名される。 かつて掲げられていた扁額には「壬辰八月吉旦」と記されており、「壬辰(じんしん)」は明治25年(1892年)を表し、その8月のことと思慮される。
大正3年頃、初めて建立されたお堂(堂宇)は石柱に瓦屋根。 その後昭和7年の秋、御大典記念の大改築が行われ、これが件の記念碑として今に伝わる。
更に被災状況は不詳ながら沖縄戦の後、昭和27年10月にお堂を再建。 現在の白銀堂は平成4年6月に改修されたお堂だと云う。
白銀堂
国道沿いの歩道、鳥居越しに臨む白銀堂のお社。
石段の補修は戦災に因る物かは不明。 お社は鳥居を経た参道の正面ではなく、右手(南)の隅に位置する。

国道沿いの境内入口
かつては水面の洗っていた磯辺も今や国道と化し、海は沖合へ遠ざかった。

古より糸満の人々が絶えず訪れる聖地。
今も糸満の生活、祭祀の中心にあって崇め奉られている。
糸満ロータリーの北方、徒歩数分の位置に鎮座する御社。 那覇からの国道331号線に面し、歩道脇の鳥居は顕著に佇み、その名を冠するバス停も存する。 信仰の対象として南部では著名な場所ながら、神主の常駐する神社ではなく、小ぢんまりとした拝所。 当然ながら、観光客の訪れる処ではない。
その白銀堂、方言では「イービンメー」と呼ばれるらしいが、その正確な創建年代は不明。 1713年成立の『琉球国由来記』、その文章の中には「シロカネ」の記載が見られ、それは18世紀の以前と思われる。 その後明治25年、第4代沖縄県知事に就任した奈良原繁 、彼によって「白銀堂」の名が命名される。 かつて掲げられていた扁額には「壬辰八月吉旦」と記されており、「壬辰(じんしん)」は明治25年(1892年)を表し、その8月のことと思慮される。
大正3年頃、初めて建立されたお堂(堂宇)は石柱に瓦屋根。 その後昭和7年の秋、御大典記念の大改築が行われ、これが件の記念碑として今に伝わる。
更に被災状況は不詳ながら沖縄戦の後、昭和27年10月にお堂を再建。 現在の白銀堂は平成4年6月に改修されたお堂だと云う。
白銀堂
国道沿いの歩道、鳥居越しに臨む白銀堂のお社。
石段の補修は戦災に因る物かは不明。 お社は鳥居を経た参道の正面ではなく、右手(南)の隅に位置する。

国道沿いの境内入口
かつては水面の洗っていた磯辺も今や国道と化し、海は沖合へ遠ざかった。

Posted by 酉 at 12:00│Comments(0)
│旧跡・文化