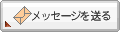2019年07月21日
沖縄に潰えた軍旗 129
歩兵第22聯隊 129
通称号 山3474部隊、第24師団 歩兵第22聯隊の軌跡
(殊闘 / その16)
昭和20年5月26日、沖縄を覆う雨雲は守備軍に与したが、戦況の好転する望みはなかった。 戦線左翼、那覇市街に侵入した敵は、特設第6聯隊によって阻止されていた。 一方の戦線右翼では24日夜、与那原市街の奪還攻撃に失敗。 既に雨乞森も敵手にある状況下、 運玉森△161高地 の確保はおろか、軍司令部の所在する首里の側背へ危機の及ぶ状況であった。 天祐は降り続く雨のみで、敵の戦車や兵站車輛の機動が一様に低下。 守備軍が敵の低調な攻撃を支えたものと考えられる。
正史に拠れば、この時期の第一線での戦闘能力は、独立機関銃第4大隊(球10290)(-3Co)は重機2銃(14銃喪失)、軽機3銃、重擲弾筒3門、約30名(HQ+2コCo 226名篇制)の編制。 緒戦より第一線に在った 独立速射砲第22大隊(球15576)の残存火砲は、速射砲1門(11門喪失)のみであった。
一方で聯隊の兵力は、石嶺後退時に1コ小隊(約100名)程度であったと云われる。 しかし正史の行間に、それに関する記述はない。
手許の戦没者名簿も仔細の判読は難しいが、5月25日迄の戦死者は、速射砲中隊で65名(95名編制、7名生還)、第10中隊で139名(186名編制、9名生還)が数えられ、やはり聯隊の編制 約2,900名のうち2/3は幸地・石嶺の地に斃れたものと考えられる。
そしてこの日、26日の日が暮れる頃から首里城地下の軍司令部では、俄かに慌ただしい動きが認められた。
首里城址
弁ヶ岳山頂より真西、約1.100メートルに位置した第32軍司令部、両師団司令部の所在した現在の首里城公園。
司令部東方の弁ヶ岳、北方の石嶺を敵に突破されれば、歩兵の重火器でも有効射程内に入るため、文字通りの「死守」が厳命されていた。

通称号 山3474部隊、第24師団 歩兵第22聯隊の軌跡
(殊闘 / その16)
昭和20年5月26日、沖縄を覆う雨雲は守備軍に与したが、戦況の好転する望みはなかった。 戦線左翼、那覇市街に侵入した敵は、特設第6聯隊によって阻止されていた。 一方の戦線右翼では24日夜、与那原市街の奪還攻撃に失敗。 既に雨乞森も敵手にある状況下、 運玉森△161高地 の確保はおろか、軍司令部の所在する首里の側背へ危機の及ぶ状況であった。 天祐は降り続く雨のみで、敵の戦車や兵站車輛の機動が一様に低下。 守備軍が敵の低調な攻撃を支えたものと考えられる。
正史に拠れば、この時期の第一線での戦闘能力は、独立機関銃第4大隊(球10290)(-3Co)は重機2銃(14銃喪失)、軽機3銃、重擲弾筒3門、約30名(HQ+2コCo 226名篇制)の編制。 緒戦より第一線に在った 独立速射砲第22大隊(球15576)の残存火砲は、速射砲1門(11門喪失)のみであった。
一方で聯隊の兵力は、石嶺後退時に1コ小隊(約100名)程度であったと云われる。 しかし正史の行間に、それに関する記述はない。
手許の戦没者名簿も仔細の判読は難しいが、5月25日迄の戦死者は、速射砲中隊で65名(95名編制、7名生還)、第10中隊で139名(186名編制、9名生還)が数えられ、やはり聯隊の編制 約2,900名のうち2/3は幸地・石嶺の地に斃れたものと考えられる。
そしてこの日、26日の日が暮れる頃から首里城地下の軍司令部では、俄かに慌ただしい動きが認められた。
首里城址
弁ヶ岳山頂より真西、約1.100メートルに位置した第32軍司令部、両師団司令部の所在した現在の首里城公園。
司令部東方の弁ヶ岳、北方の石嶺を敵に突破されれば、歩兵の重火器でも有効射程内に入るため、文字通りの「死守」が厳命されていた。

Posted by 酉 at 12:00│Comments(0)
│景 色