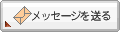2012年07月26日
戦世(いくさゆー) 295
本部町並里 並里神社 前篇
県道84号線、その北側に位置する並里集落。
その集落を見下ろす山並み、北側山嶺の中腹に鎮座する。
本部半島を横断する県道84号線。 県道沿いには八重岳の寒緋桜、伊豆見の柑橘類と、その時節の往来は激しい。 しかし何れもその南側に位置し、観光客は北側の集落へ寄る者、そして見向きする者も僅かと思われる。 並里集落は、その様な閑静な場所に位置する。
集落へは更に満名川を隔て、南を向く緩斜面、そこに続く小径沿いに民家、そして畠地が広がる。 そのほぼ中心に並里公民館が立ち、見上げる山嶺の中程、白っぽい御社が緑の中に覗く。 それが今回の目的地、並里神社であった。
この並里神社の祭祀は並里の御嶽と云われ、 「渡久地神社」 同様の成り立ちと思われる。 御社への階段はアサギを抜けて続き、拝殿或いは俗世との境界、鳥居と同様の意味合いであろう。 その右手には「並里神社」の社号が掲げられ、その背面には昭和10年1月吉日の文字。 委細判読不明ながら、「神社」としての改修は昭和10年に為されたと見られる。
階段を上り詰めると御社が鎮座、その意匠は渡久地神社同様、神社の神殿を意識した重厚なもの。 コンクリートで成形され、化粧モルタルが全面を覆い、処々には装飾が施されている。
昭和初期のコンクリート建造物、そして凝った意匠には確かに興味を隠せない。 暫し御社の前面から棟の端部、破風部の装飾を見上げていた。 しかし、ここへ来た本当の目的は、その様なことではなかった。
並里神社のアサギ
御社への参道、階段の途中には神アサギがあり、そこを抜けると御社が望める。
右手の碑には「並里神社」と記されるも、コンクリートの表面は風化著しい。

並里神社御社
扉は無粋なアルミサッシとなるも、建立時からの凝った意匠、屋根の装飾などは今に伝わる。 その背景を知ったうえ、失礼ながら宗教さえ「チャンプルー感」満載と思へる。

県道84号線、その北側に位置する並里集落。
その集落を見下ろす山並み、北側山嶺の中腹に鎮座する。
本部半島を横断する県道84号線。 県道沿いには八重岳の寒緋桜、伊豆見の柑橘類と、その時節の往来は激しい。 しかし何れもその南側に位置し、観光客は北側の集落へ寄る者、そして見向きする者も僅かと思われる。 並里集落は、その様な閑静な場所に位置する。
集落へは更に満名川を隔て、南を向く緩斜面、そこに続く小径沿いに民家、そして畠地が広がる。 そのほぼ中心に並里公民館が立ち、見上げる山嶺の中程、白っぽい御社が緑の中に覗く。 それが今回の目的地、並里神社であった。
この並里神社の祭祀は並里の御嶽と云われ、 「渡久地神社」 同様の成り立ちと思われる。 御社への階段はアサギを抜けて続き、拝殿或いは俗世との境界、鳥居と同様の意味合いであろう。 その右手には「並里神社」の社号が掲げられ、その背面には昭和10年1月吉日の文字。 委細判読不明ながら、「神社」としての改修は昭和10年に為されたと見られる。
階段を上り詰めると御社が鎮座、その意匠は渡久地神社同様、神社の神殿を意識した重厚なもの。 コンクリートで成形され、化粧モルタルが全面を覆い、処々には装飾が施されている。
昭和初期のコンクリート建造物、そして凝った意匠には確かに興味を隠せない。 暫し御社の前面から棟の端部、破風部の装飾を見上げていた。 しかし、ここへ来た本当の目的は、その様なことではなかった。
並里神社のアサギ
御社への参道、階段の途中には神アサギがあり、そこを抜けると御社が望める。
右手の碑には「並里神社」と記されるも、コンクリートの表面は風化著しい。

並里神社御社
扉は無粋なアルミサッシとなるも、建立時からの凝った意匠、屋根の装飾などは今に伝わる。 その背景を知ったうえ、失礼ながら宗教さえ「チャンプルー感」満載と思へる。

Posted by 酉 at 12:00│Comments(0)
│旧跡・文化