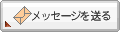2018年04月21日
大和世(やまとゆー) 395
名護市東江 セメント瓦住宅 (後篇)
沖縄の戦後復興の象徴
名護を発祥とするセメント瓦葺きの住宅
セメントで瓦を作る製法は、日本の統治領であった台湾より伝わったと云われる。 名護出身の岸本氏は、赴任先で出会ったセメント瓦の技法を持ち帰り、製造販売を開始したのが昭和10年。 宮城氏が屋根の葺き替えを考えた時期と符合したのである。
明治22年に民間での瓦葺き禁止令が解除されていたものの、瓦は高価であった為、沖縄では依然として茅葺き屋根の民家が多かった。 しかし昭和13年、戦時下にあった日本は市街地法により茅葺き屋根を禁止。 これによって焼き瓦に比べ、施工も簡便で安価、しかも台風にも強いセメント瓦が普及した。
昭和20年の敗戦後、灰燼からの復興に規格住宅の建築が進められた。 その屋根は天幕やトタン、茅葺きであったが昭和21年以降、次第に居住性改善、白蟻や台風による被害を軽減する目的でセメント瓦が広く用いられるようになった。 琉球政府は「復興瓦」として、工場の規模に応じ生産を割り当てていた。 この頃、名護には25社のセメント瓦工場が操業していた。
転機が訪れるのは昭和34年のこと、奇しくも琉球セメントが屋部村(当時)安和に設立された事であった。 昭和35年にはセメント瓦製造業者で組合を設立、28社が操業し最盛期であったと見られる。 昭和40年、琉球セメント屋部工場が操業を開始。 次第に沖縄の家屋は鉄筋コンクリート住宅に取って代わり、セメント瓦工場は姿を消し組合も平成2年頃に解散した。
平成30年の現在、名護で操業するセメント瓦工場は唯1社、週1で250枚を製造し続けている。
他方でコンクリートブロックの製法は敗戦後、米軍工兵隊によって持ち込まれた。 昭和25年頃に民間での製造販売に至り、亜熱帯の沖縄では「花ブロック」と云う、風通しと共に意匠を兼ねた独特の文化を生み出している。
今でも名護の街ではセメント瓦の甍が少なくはない。 その棟の両端に据えられた鬼瓦、軒の隅部に設けられた瓦など、苗字や屋号に関係する独特の意匠には興味を惹かれる。 さらに耐候性にも優れるセメント製の瓦だが、残念ながら都市化の波には逆らえないようである。
太郎家の軒先
お住まいの方に偶然出会ったものの、軒先からの撮影のみで辞去した。

比嘉セメント瓦工場
名護で唯一操業する比嘉セメント瓦工場。
屋根瓦の隅部には「〇」に「H」の印章が浮かんでいる。

沖縄の戦後復興の象徴
名護を発祥とするセメント瓦葺きの住宅
セメントで瓦を作る製法は、日本の統治領であった台湾より伝わったと云われる。 名護出身の岸本氏は、赴任先で出会ったセメント瓦の技法を持ち帰り、製造販売を開始したのが昭和10年。 宮城氏が屋根の葺き替えを考えた時期と符合したのである。
明治22年に民間での瓦葺き禁止令が解除されていたものの、瓦は高価であった為、沖縄では依然として茅葺き屋根の民家が多かった。 しかし昭和13年、戦時下にあった日本は市街地法により茅葺き屋根を禁止。 これによって焼き瓦に比べ、施工も簡便で安価、しかも台風にも強いセメント瓦が普及した。
昭和20年の敗戦後、灰燼からの復興に規格住宅の建築が進められた。 その屋根は天幕やトタン、茅葺きであったが昭和21年以降、次第に居住性改善、白蟻や台風による被害を軽減する目的でセメント瓦が広く用いられるようになった。 琉球政府は「復興瓦」として、工場の規模に応じ生産を割り当てていた。 この頃、名護には25社のセメント瓦工場が操業していた。
転機が訪れるのは昭和34年のこと、奇しくも琉球セメントが屋部村(当時)安和に設立された事であった。 昭和35年にはセメント瓦製造業者で組合を設立、28社が操業し最盛期であったと見られる。 昭和40年、琉球セメント屋部工場が操業を開始。 次第に沖縄の家屋は鉄筋コンクリート住宅に取って代わり、セメント瓦工場は姿を消し組合も平成2年頃に解散した。
平成30年の現在、名護で操業するセメント瓦工場は唯1社、週1で250枚を製造し続けている。
他方でコンクリートブロックの製法は敗戦後、米軍工兵隊によって持ち込まれた。 昭和25年頃に民間での製造販売に至り、亜熱帯の沖縄では「花ブロック」と云う、風通しと共に意匠を兼ねた独特の文化を生み出している。
今でも名護の街ではセメント瓦の甍が少なくはない。 その棟の両端に据えられた鬼瓦、軒の隅部に設けられた瓦など、苗字や屋号に関係する独特の意匠には興味を惹かれる。 さらに耐候性にも優れるセメント製の瓦だが、残念ながら都市化の波には逆らえないようである。
太郎家の軒先
お住まいの方に偶然出会ったものの、軒先からの撮影のみで辞去した。

比嘉セメント瓦工場
名護で唯一操業する比嘉セメント瓦工場。
屋根瓦の隅部には「〇」に「H」の印章が浮かんでいる。

Posted by 酉 at 12:00│Comments(0)
│産業遺跡