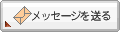2017年02月13日
大和世(やまとゆー) 391
今帰仁村古宇利 古宇利島第一桟橋 (後篇)
ひと気のない古宇利漁港の西端
かつては島の玄関口であった第一桟橋
昭和23年8月、島と運天の間に就航した定期船(機帆船)は、専ら人と小型の荷物の運搬に従事していた。 定期船は、その後の代替わりを経て昭和45年1月、小型のフェリー(シューテイ)へと替る。 桟橋はフェリーのランプを受けるため、専用の第二桟橋が建設されるが、第一桟橋にも小型の貨物船や漁船が接舷され、引き続き島の玄関口として運用されていた。
しかし平成17年2月、古宇利大橋の開通により定期海上航路は役目を終え、かつて大泊(ウプドゥマイ)と称された島の玄関口も、その役目を終える。
観光客の蝟集する大橋の袂を一瞥に通過、第一桟橋は古宇利漁港の西端に遺されていた。 今は干瀬から沖合へ防波堤が伸び、当日の海象も相俟って穏やかな桟橋だが、シナ海に面した港湾の常として、冬場の運用は厳しかったと思われる。
第一桟橋の築造は、今帰仁村の資料にも明らかではなく、「戦後間もない頃」或いは「昭和34年」とも記され、復帰前の事ゆえか国土地理院の資料も空白であった。 そして現地へ足を運んでみた処、どうやら前者の可能性が高いと考えた。
長大な防波堤を始めとして、島の浜は護岸へと変わり、干瀬を埋め立てた人口の浜、畠地を潰した集客施設に人々は集っている。 島は架橋により様相を変え、今後も変化を続けていくのであろう。 対照的に第一桟橋は島の玄関口としての役割を終え、今や朽ち果てて行くばかりである。
薄暮の第一桟橋
発達した積乱雲の下には、本部半島の山々が連なる。
左端は第二桟橋、穏やかな海面だが、防波堤により外海と隔てられている。

桟橋下部
築造より50余年は経過し、傷みの目立つ桟橋の基部。 鋼管杭やRC杭は用いられておらず、恐らくは基礎に松杭を打設してコンクリートを巻くなどし、昭和30年代の規格とは考えられない。 近い将来には立入が制限され、やがては撤去される事であろう。

ひと気のない古宇利漁港の西端
かつては島の玄関口であった第一桟橋
昭和23年8月、島と運天の間に就航した定期船(機帆船)は、専ら人と小型の荷物の運搬に従事していた。 定期船は、その後の代替わりを経て昭和45年1月、小型のフェリー(シューテイ)へと替る。 桟橋はフェリーのランプを受けるため、専用の第二桟橋が建設されるが、第一桟橋にも小型の貨物船や漁船が接舷され、引き続き島の玄関口として運用されていた。
しかし平成17年2月、古宇利大橋の開通により定期海上航路は役目を終え、かつて大泊(ウプドゥマイ)と称された島の玄関口も、その役目を終える。
観光客の蝟集する大橋の袂を一瞥に通過、第一桟橋は古宇利漁港の西端に遺されていた。 今は干瀬から沖合へ防波堤が伸び、当日の海象も相俟って穏やかな桟橋だが、シナ海に面した港湾の常として、冬場の運用は厳しかったと思われる。
第一桟橋の築造は、今帰仁村の資料にも明らかではなく、「戦後間もない頃」或いは「昭和34年」とも記され、復帰前の事ゆえか国土地理院の資料も空白であった。 そして現地へ足を運んでみた処、どうやら前者の可能性が高いと考えた。
長大な防波堤を始めとして、島の浜は護岸へと変わり、干瀬を埋め立てた人口の浜、畠地を潰した集客施設に人々は集っている。 島は架橋により様相を変え、今後も変化を続けていくのであろう。 対照的に第一桟橋は島の玄関口としての役割を終え、今や朽ち果てて行くばかりである。
薄暮の第一桟橋
発達した積乱雲の下には、本部半島の山々が連なる。
左端は第二桟橋、穏やかな海面だが、防波堤により外海と隔てられている。

桟橋下部
築造より50余年は経過し、傷みの目立つ桟橋の基部。 鋼管杭やRC杭は用いられておらず、恐らくは基礎に松杭を打設してコンクリートを巻くなどし、昭和30年代の規格とは考えられない。 近い将来には立入が制限され、やがては撤去される事であろう。

Posted by 酉 at 12:00│Comments(0)
│産業遺跡