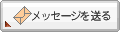2017年02月12日
大和世(やまとゆー) 390
今帰仁村古宇利 古宇利島第一桟橋 (前篇)
ひと気のない古宇利漁港の西端
かつては島の玄関口であった第一桟橋
沖縄本島周辺の島々は、戦史にその名称が表されなくとも戦闘の終結後、各々の戦後の歩みが始められている。
ここ古宇利島に敵が上陸したのは昭和20年4月23日と云われ、それまでも 運天港 、屋我地島 ( 愛楽園 ) の攻撃目標の狭間に在って、艦砲、空襲による被害があった。 敵は近隣の屋我地島へ「L+20」に到達しており、4月中に島嶼部も含めた本部半島の掃討を完了している。
島民は同年5月から6月頃にかけ、田井等の民間人収容所へ収容される。 しかし同年11月頃には帰島を許され、シマの戦後が歩み出す。
島の小学校は昭和20年12月に再開されるなど、比較的落ち着いた戦後であったと見られる。 島民は農耕家畜漁などにより生計を立てる他、サバニを駆って密航し、生活必需品を入手する者もあった。
島と本島との間に、戦前より定期船の就航はなく、島の大泊(現在の古宇利魚港)とクンジャー浜(現在の運天漁港)の間をサバニ、伝馬船が行き来し、シマや浜からの合図に応じ舟を出していた。 しかし昭和22年10月、村の運動会へ向かう人々を乗せた伝馬船が沖合で転覆する。 これが契機となり、昭和23年8月に大型の機帆船(焼玉エンジン付きの和船)が、定期船として就航する。
それまでのサバニや伝馬船は浜へ直接乗り揚げ、人や物資の積み降ろしをしていた。 しかし機帆船の就航に伴い従前の運用は出来ず、航路の一部が変更され、本島側は運天港を発着地とし、島の大泊(ウプドゥマイ)には桟橋が設けられることとなる。
古宇利第一桟橋
古宇利(漁)港の西端に設けられた第一桟橋(手前)と、後に小型フェリーが使用した第二桟橋(奥)。
積乱雲の下には本島山原の森、海との間には古宇利大橋が伸びている。

桟橋上部
かつては悲喜交々、人や物資の往来した事であろうが、今や桟橋上は物干しとなり、連絡道路も断ち切られている。

ひと気のない古宇利漁港の西端
かつては島の玄関口であった第一桟橋
沖縄本島周辺の島々は、戦史にその名称が表されなくとも戦闘の終結後、各々の戦後の歩みが始められている。
ここ古宇利島に敵が上陸したのは昭和20年4月23日と云われ、それまでも 運天港 、屋我地島 ( 愛楽園 ) の攻撃目標の狭間に在って、艦砲、空襲による被害があった。 敵は近隣の屋我地島へ「L+20」に到達しており、4月中に島嶼部も含めた本部半島の掃討を完了している。
島民は同年5月から6月頃にかけ、田井等の民間人収容所へ収容される。 しかし同年11月頃には帰島を許され、シマの戦後が歩み出す。
島の小学校は昭和20年12月に再開されるなど、比較的落ち着いた戦後であったと見られる。 島民は農耕家畜漁などにより生計を立てる他、サバニを駆って密航し、生活必需品を入手する者もあった。
島と本島との間に、戦前より定期船の就航はなく、島の大泊(現在の古宇利魚港)とクンジャー浜(現在の運天漁港)の間をサバニ、伝馬船が行き来し、シマや浜からの合図に応じ舟を出していた。 しかし昭和22年10月、村の運動会へ向かう人々を乗せた伝馬船が沖合で転覆する。 これが契機となり、昭和23年8月に大型の機帆船(焼玉エンジン付きの和船)が、定期船として就航する。
それまでのサバニや伝馬船は浜へ直接乗り揚げ、人や物資の積み降ろしをしていた。 しかし機帆船の就航に伴い従前の運用は出来ず、航路の一部が変更され、本島側は運天港を発着地とし、島の大泊(ウプドゥマイ)には桟橋が設けられることとなる。
古宇利第一桟橋
古宇利(漁)港の西端に設けられた第一桟橋(手前)と、後に小型フェリーが使用した第二桟橋(奥)。
積乱雲の下には本島山原の森、海との間には古宇利大橋が伸びている。

桟橋上部
かつては悲喜交々、人や物資の往来した事であろうが、今や桟橋上は物干しとなり、連絡道路も断ち切られている。

Posted by 酉 at 13:00│Comments(0)
│産業遺跡