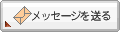2018年04月20日
大和世(やまとゆー) 394
名護市東江 セメント瓦住宅 (前篇)
沖縄の戦後復興の象徴
名護を発祥とするセメント瓦葺きの住宅
勤め先が変わりこの夏で4年、渡沖の機会も減って久しい訳である。 生業の多忙と夏場の暑気を避け、6月より半年を隔て年末に赴いた際は、街並みや景色の変貌に驚くことも少なくはない。 昨年のこと、いつもの様に沖縄中南部での踏査に数日を過ごし、名護へ移動した時である。 夕刻の世冨慶交差点から旧道に逸れ、 新山食堂 にでも寄ろうかと思った路傍には、平屋の民家が消え共同住宅の建築を謳う看板が立っていた。
その場所、名護市東江1丁目の幸地川の左岸には、戦前からの民家が現存していた。 全島が戦禍に覆われた沖縄に於いて、戦前からの建造物が少ない中、残存する戦前の建物が現住建造物であったこと。 併せてセメント瓦が戦前から生産され、名護を発祥としていた事に興味を持ち、車窓にそのひっそりとした佇まいを追ったものであった。
その民家の名前は通称を「太郎家」 (タローヤー)、家を建てた宮城氏の名前に由来する。 アルゼンチン移民であった氏は、帰国した昭和5年頃にこの家を建てた。 その後 昭和10年、屋根を葺き替える際、名護で製造販売を開始したセメント瓦を用い、初めて施工された家であった。
沖縄では赤瓦・・と云う広告代理店の創ったイメージとは異なり、琉球王府は民間での瓦葺きを禁止していた。 16世紀頃に渡来した 赤瓦焼成の技法 も、明治22年まで民家の屋根には無用のモノであった。
セメント瓦屋根
平成29年3月迄現存した戦前からの民家、通称:太郎家の遠景。 (2013年4月撮)

門構
門柱と塀囲いの多くも戦前に建築されたものであり、その意匠も土地と時代を反映したものであった。

沖縄の戦後復興の象徴
名護を発祥とするセメント瓦葺きの住宅
勤め先が変わりこの夏で4年、渡沖の機会も減って久しい訳である。 生業の多忙と夏場の暑気を避け、6月より半年を隔て年末に赴いた際は、街並みや景色の変貌に驚くことも少なくはない。 昨年のこと、いつもの様に沖縄中南部での踏査に数日を過ごし、名護へ移動した時である。 夕刻の世冨慶交差点から旧道に逸れ、 新山食堂 にでも寄ろうかと思った路傍には、平屋の民家が消え共同住宅の建築を謳う看板が立っていた。
その場所、名護市東江1丁目の幸地川の左岸には、戦前からの民家が現存していた。 全島が戦禍に覆われた沖縄に於いて、戦前からの建造物が少ない中、残存する戦前の建物が現住建造物であったこと。 併せてセメント瓦が戦前から生産され、名護を発祥としていた事に興味を持ち、車窓にそのひっそりとした佇まいを追ったものであった。
その民家の名前は通称を「太郎家」 (タローヤー)、家を建てた宮城氏の名前に由来する。 アルゼンチン移民であった氏は、帰国した昭和5年頃にこの家を建てた。 その後 昭和10年、屋根を葺き替える際、名護で製造販売を開始したセメント瓦を用い、初めて施工された家であった。
沖縄では赤瓦・・と云う広告代理店の創ったイメージとは異なり、琉球王府は民間での瓦葺きを禁止していた。 16世紀頃に渡来した 赤瓦焼成の技法 も、明治22年まで民家の屋根には無用のモノであった。
セメント瓦屋根
平成29年3月迄現存した戦前からの民家、通称:太郎家の遠景。 (2013年4月撮)

門構
門柱と塀囲いの多くも戦前に建築されたものであり、その意匠も土地と時代を反映したものであった。

Posted by 酉 at 12:00│Comments(0)
│産業遺跡