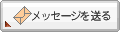2014年04月25日
大和世(やまとゆー) 301
南城市佐敷 能久親王御寄港之碑と忠魂碑 前篇
旧佐敷町役場(所)跡、その片隅に据えられた2基の石碑、
北白川能久親王御寄港之地碑、そして削られた 佐敷の忠魂碑
与那原交差点より、知念半島の海沿いを抜ける国道311号線。 那覇市街を抜ける箇所と異なり通行量は少なく、それだけに平均速度は高めに見える。 その「わ」ナンバーが月代宮の大鳥居を一瞥に過ぎる辺り、今は南城市となった旧佐敷町、かつての中心地である。
信号脇の古い標、それに従って路地へと入る、すると右手に直ぐ佐敷町役場跡へと行き着く。 今は庁舎もなく、正面に跡地碑が据えられるだけの駐車場であるが、その南西の隅、雑草の繁茂する植え込みの中には、2基の古びた石碑が放置されている。
南側に位置する背の高い石碑、その表面には「能久親王御寄港之碑」そして揮毫者の階位と氏名が刻まれ、背面には建立の由来、経緯が記されている。
「能久親王」とは北白川宮能久親王のこと。 明治28年4月17日、下関条約の締結により日清戦争が終結。 台湾は清から日本へ割譲され、平定すの為に近衛師団が向けられた。 当時、陸軍中将として 近衛師団長 に在った能久親王は、沖縄に於いて初代総督 樺山資紀と合流。 翌日、台湾へ出港したとされ、時に明治28年5月27日と刻まれている。
碑の揮毫は今帰仁村運天の 源為朝公上陸之址碑 と同じ、海軍大将の筆によるもの。 また建立は「沖縄史蹟保存會」なる団体の手によるものであった。
沖縄史蹟保存會とは大正11年1月、新潟出身の検事 島倉龍治の発起により、(沖縄学の研究者)眞境名安興らと共に創立。 同碑は大正12年5月5日に建立され、先の 源為朝公上陸之址碑 など、同時期に20程の記念碑を建立ししている。 更に氏は地方文化を重視し、沖縄神社(那覇市弁ヶ岳)の創建にも深く関わったと云われる。 しかしながら同化政策に与した節もあり、また所詮は内地からの官吏の者ゆえか、沖縄での知名度は悉く低い。
北白川親王寄港之地碑
正確には表題の通り「能久親王御寄港之地碑」と刻まれ、北に位置する馬天港を向いて据えられている。

同碑 背面
背面には前掲、碑の建立に関する経緯が刻まれているが、一部に欠け、判読の難しい箇所がある。

旧佐敷町役場(所)跡、その片隅に据えられた2基の石碑、
北白川能久親王御寄港之地碑、そして削られた 佐敷の忠魂碑
与那原交差点より、知念半島の海沿いを抜ける国道311号線。 那覇市街を抜ける箇所と異なり通行量は少なく、それだけに平均速度は高めに見える。 その「わ」ナンバーが月代宮の大鳥居を一瞥に過ぎる辺り、今は南城市となった旧佐敷町、かつての中心地である。
信号脇の古い標、それに従って路地へと入る、すると右手に直ぐ佐敷町役場跡へと行き着く。 今は庁舎もなく、正面に跡地碑が据えられるだけの駐車場であるが、その南西の隅、雑草の繁茂する植え込みの中には、2基の古びた石碑が放置されている。
南側に位置する背の高い石碑、その表面には「能久親王御寄港之碑」そして揮毫者の階位と氏名が刻まれ、背面には建立の由来、経緯が記されている。
「能久親王」とは北白川宮能久親王のこと。 明治28年4月17日、下関条約の締結により日清戦争が終結。 台湾は清から日本へ割譲され、平定すの為に近衛師団が向けられた。 当時、陸軍中将として 近衛師団長 に在った能久親王は、沖縄に於いて初代総督 樺山資紀と合流。 翌日、台湾へ出港したとされ、時に明治28年5月27日と刻まれている。
碑の揮毫は今帰仁村運天の 源為朝公上陸之址碑 と同じ、海軍大将の筆によるもの。 また建立は「沖縄史蹟保存會」なる団体の手によるものであった。
沖縄史蹟保存會とは大正11年1月、新潟出身の検事 島倉龍治の発起により、(沖縄学の研究者)眞境名安興らと共に創立。 同碑は大正12年5月5日に建立され、先の 源為朝公上陸之址碑 など、同時期に20程の記念碑を建立ししている。 更に氏は地方文化を重視し、沖縄神社(那覇市弁ヶ岳)の創建にも深く関わったと云われる。 しかしながら同化政策に与した節もあり、また所詮は内地からの官吏の者ゆえか、沖縄での知名度は悉く低い。
北白川親王寄港之地碑
正確には表題の通り「能久親王御寄港之地碑」と刻まれ、北に位置する馬天港を向いて据えられている。

同碑 背面
背面には前掲、碑の建立に関する経緯が刻まれているが、一部に欠け、判読の難しい箇所がある。

Posted by 酉 at 12:00│Comments(0)
│旧跡・文化