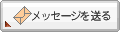2011年11月26日
大和世(やまとゆー) 153
大宜味村大兼久 旧大宜味村役場庁舎 後篇
かつて用いられた、大宜味村役場庁舎。
県内に現存する、数少ない戦前の建築物のひとつである。
旧庁舎は、今にすれば簡素な佇まい、そのうえ時流に応じ、処々に手を加えられている。 確かに、内地の重文指定の建築物に比して、見劣りは否めない。 しかし、豪華に着飾った彼等とは異なり、簡素な中に盛り込まれた、風土、時代に即した実利。 そしてRC建築の技術が熟成される以前、設計者/ 清村 勉の独学、研究、実証を兼ねての「仕事」は、技術者として驚嘆に値する。 今後、県指定文化財より、更に踏み込んだ文化財としての修復、復元、そして活用を願いたい。
しかしながら、県内に近代建築物が稀有な事、それは必ずしも、戦火のみによる訳ではない。
同庁舎を設計した清村氏は、前年の大正13年、県内初のRC校舎を「金武小学校」として竣工させる。 戦火に凌駕された那覇でも、「武徳殿」は佳く耐え凌いだ。 そして戦後オキナワの因縁たる「琉球政府立法院議事堂」、全て沖縄の正史に刻まれる建築物であった。
昭和57年/ 金武小学校旧校舎、平成元年/ 武徳殿、そして平成11年、立法院議事堂。 何れも破壊したのは近年の事、保存運動を圧しての破壊は、沖縄の人達の手によってである。
彼の首里城でさえ戦前(大正14年)は荒廃に見兼ね、首里市議会(当時)は解体を議決。 寸での処を救ったのは、皮肉にも二名の大和人。 沖縄文化研究者/ 鎌倉芳太郎、そして 「東京都慰霊堂」 を設計した建築家/ 伊東忠太である。 邪道ながら、内務省(当時)を通じた、トップダウンによる解体阻止。 後年、沖縄戦に灰燼と帰するも、沖縄人自らが手を汚す遺恨を除けている。
奇しくも今、那覇市では久茂地公民館ビル(旧沖縄少年会館)の解体が、同様に取沙汰されている。 果たして同じ轍を踏むのか、省みる胆を持ったか、今再び試されている。
庁舎全景
南西から臨む庁舎の全景。 二階、八角形の村長執務室、西側の扉設え、上縁を囲む笠木の装飾が判る。 方々の窓から出ている電線は、時流80余年の皺にも見へる。
2011年11月現在、近代土木遺産の選に入らず。

庁舎北面
非常にがっかりな事、庁舎の面構えたる北面には、職員の自家用車、公用車が居並び、その容貌を台無しにしている。
何とも思わないのか、 大宜味村役場HP 上の写真も、同じあり様である。

かつて用いられた、大宜味村役場庁舎。
県内に現存する、数少ない戦前の建築物のひとつである。
旧庁舎は、今にすれば簡素な佇まい、そのうえ時流に応じ、処々に手を加えられている。 確かに、内地の重文指定の建築物に比して、見劣りは否めない。 しかし、豪華に着飾った彼等とは異なり、簡素な中に盛り込まれた、風土、時代に即した実利。 そしてRC建築の技術が熟成される以前、設計者/ 清村 勉の独学、研究、実証を兼ねての「仕事」は、技術者として驚嘆に値する。 今後、県指定文化財より、更に踏み込んだ文化財としての修復、復元、そして活用を願いたい。
しかしながら、県内に近代建築物が稀有な事、それは必ずしも、戦火のみによる訳ではない。
同庁舎を設計した清村氏は、前年の大正13年、県内初のRC校舎を「金武小学校」として竣工させる。 戦火に凌駕された那覇でも、「武徳殿」は佳く耐え凌いだ。 そして戦後オキナワの因縁たる「琉球政府立法院議事堂」、全て沖縄の正史に刻まれる建築物であった。
昭和57年/ 金武小学校旧校舎、平成元年/ 武徳殿、そして平成11年、立法院議事堂。 何れも破壊したのは近年の事、保存運動を圧しての破壊は、沖縄の人達の手によってである。
彼の首里城でさえ戦前(大正14年)は荒廃に見兼ね、首里市議会(当時)は解体を議決。 寸での処を救ったのは、皮肉にも二名の大和人。 沖縄文化研究者/ 鎌倉芳太郎、そして 「東京都慰霊堂」 を設計した建築家/ 伊東忠太である。 邪道ながら、内務省(当時)を通じた、トップダウンによる解体阻止。 後年、沖縄戦に灰燼と帰するも、沖縄人自らが手を汚す遺恨を除けている。
奇しくも今、那覇市では久茂地公民館ビル(旧沖縄少年会館)の解体が、同様に取沙汰されている。 果たして同じ轍を踏むのか、省みる胆を持ったか、今再び試されている。
庁舎全景
南西から臨む庁舎の全景。 二階、八角形の村長執務室、西側の扉設え、上縁を囲む笠木の装飾が判る。 方々の窓から出ている電線は、時流80余年の皺にも見へる。
2011年11月現在、近代土木遺産の選に入らず。

庁舎北面
非常にがっかりな事、庁舎の面構えたる北面には、職員の自家用車、公用車が居並び、その容貌を台無しにしている。
何とも思わないのか、 大宜味村役場HP 上の写真も、同じあり様である。

Posted by 酉 at 12:00│Comments(0)
│産業遺跡